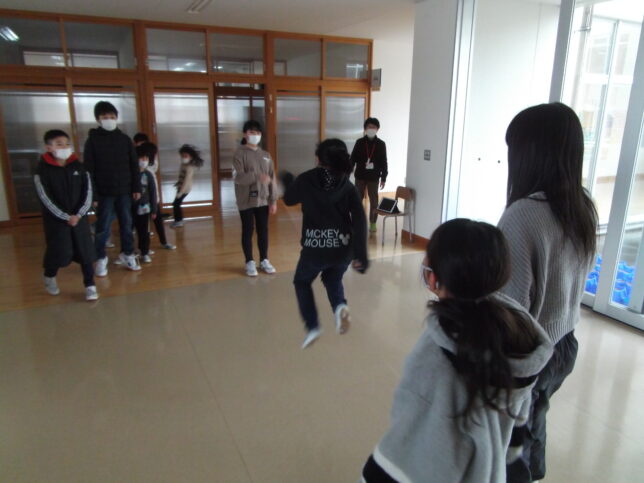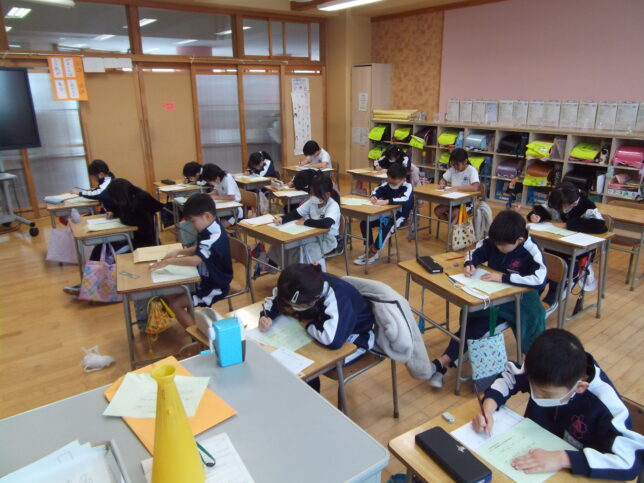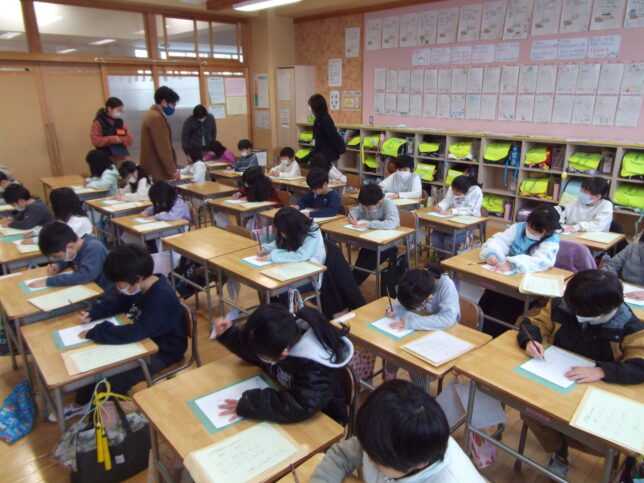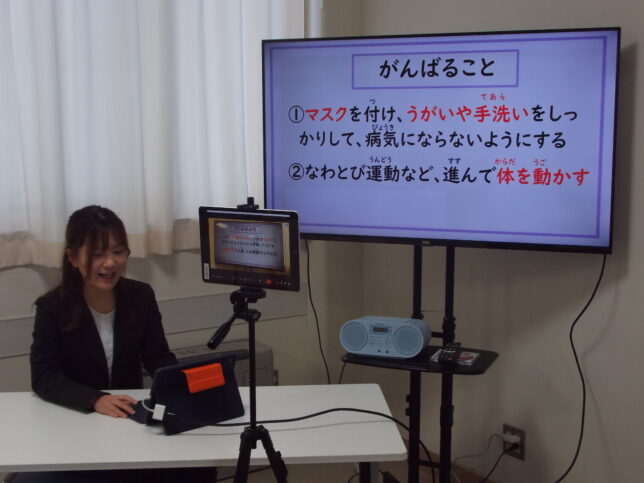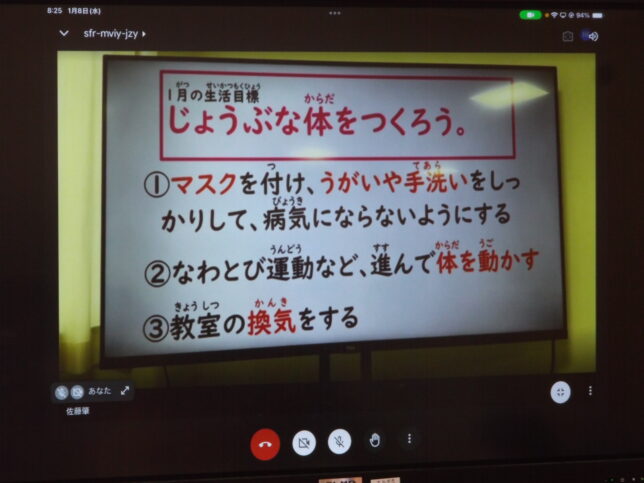給食週間最後のメニューは、沖縄をイメージした「クファジューシー」「沖縄県産もずくスープ」「にんじんしりしり」「シークワーサータルト」「牛乳」です。クファジューシーは、行事やお祝い事にはかかせない「炊き込みご飯」だそうです。ご飯なのにモチモチしていて、豚肉、かまぼこ、ごぼう、しいたけなど具材が細かく千切りされ、ごま油も入ってまろやかな塩味でまとまっています。子どもたちはお代わりの行列を作りそうです。もずくスープは、すべての食材が1㎝程度にカットされ、もずくの深緑色と、豆腐とえのきの白が混ざり合い、あっさりした味にまとまっていておししいです。にんじんしりしりは、にんじん、こんにゃくが小さくカットされ、ふんわりたまごとツナが混ざり合い、ほんのり甘い炒め物に仕上がっています。すべてがやわらかくてびっくりします。デザートは、シークワーサーの甘酸っぱさと、側面のタルトのさくさく感が絶妙にマッチしていておいしかったです。作ってくださる、栄養士さん、調理員さんに、そして全国の食べ物を生産している皆さんに感謝していただきましょう。